この記事は約 11 分で読めます。
車のことを知れば知るほど、各部の構造の違いや差はとても気になってしまう。
中でも、乗り心地やハンドリングに大きく差が出てしまうのがサスペンションの種類の違いである。

実はこんなに凄い!ダブルウィッシュボーンの特徴


スポーツカーや競技用車両に必ずと言っていいほど採用されるダブルウィッシュボーン式サスペンション。車のことに詳しくない方でも、名前ぐらいは聞かれたことがあるのではないでしょうか?
この項目では、その機能が優れているダブルウィッシュボーン式サスペンションの特徴や構造についてお話しました。
ダブルウィッシュボーンとは?
ダブルウィッシュボーン式サスペンションとは、独立懸架式サスペンションの中の一種であり、高級車やスポーツカーに多く採用される。「ダブルウィッシュボーン式独立懸架」とも呼ばれている。
「ダブルウィッシュボーン」の名前の由来は、鳥の叉骨(wishbone)のような形状のA字型のアームが上下に2つ(double)配置されていることからである。
すでに半世紀にわたって、フォーミュラーカーを含めた競技用車両は、ダブルウィッシュボーン式サスペンションの採用を続けている。理由は、そのセッティングの幅広さと自由さからだろう。
ちなみに、国産車で最初に採用となった車種は、トヨペットのSAの前輪に採用された。
ダブルウィッシュボーンの構造とは?
先述したA字型の2つの上下に配置されたアームが特徴のダブルウィッシュボーンの構造は、とても複雑だ。
適当な画像や図が無いため、わかりにくくて恐縮だが、この2つのアーム(アッパーアームとロワアーム)は、路面に対してほぼ水平に取り付けられ、車軸やハブを上下から挟み込み形で取り付けられる構造になっている。これらはほぼ、平行四辺形のような形状であることから、路面の衝撃に対してもタイヤのキャンバー角はほぼ一定に保たれている。

上下にA字型の2つのアーム(アッパーアームとロワアーム)によって取り付けられたダブルウィッシュボーン式サスペンションだが、2つのアームの長さが等長になってしまうと、キャンバー角が固定されてしまい、タイヤが著しく摩耗してしまうため良くない。
そこで、下側のアーム(ロワアーム)の長さを上側のアーム(アッパーアーム)に対して長く取ることにより、キャンバー角が変化してタイヤの摩耗を抑えることができるため、ほとんどがこのような構造になっている。
ダブルウィッシュボーンの操舵性能(ハンドリング特性)
ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用した車をドライブすると感じることは、ハンドリングの回答性がとても良いことである。
カーブでステアリングを切ると、クイックに車が向きを変えてくれる俊敏性は、スポーツ走行にとても適していると言えるだろう。
ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用した車で、僕にとても強烈な印象を与えてくれたのが、ホンダの5代目のシビックであるEF3型シビックである。通称で「グランドシビック」と呼ばれたこの車は、僕が20歳の頃に遡って、今でも強く記憶に残っている。
この車両は、4輪にダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用し、今は亡き僕の友人が所有し乗った。実家がホンダの販売店兼修理工場だったその友人は、その特権で新車で格安でEF3を購入した。何度も同乗させてもらったり運転させてもらって感じたのは、「なんてよく曲がる車なんだろう!」と驚いたものだった。
かなりのスピードを出しているにもかかわらず、思うままにフロントが入っていくのだ。ドライブするのがこんなに楽しい車は初めてだった。このことから「ダブルウィッシュボーン」と言えば、ホンダをイメージするのだ。
ホンダはサスペンションを含めた足回りの創り方に強いこだわりを持つメーカーだ。従来のサスペンションの構造上のしくみで見てみると、ダブルウィッシュボーン式のサスペンションは、車体側の上下2箇所、上下にあるリンク、アップライトから成る「4リンク」構造のものが主流である。
ただ、1997年にホンダが採用した「5リンク・ダブルウィッシュボーン・リアサスペンション」は、5リンク化することで、路面から受ける前後・横方向の力を各アームの軸方向にのみ入力させることが可能となり、アームをストレート化することで軽量化を実現している。
他の自動車国産メーカーも、ダブルウィッシュボーンを採用してはいるが、僕にとってのダブルウィッシュボーンと言えばホンダをイメージしてしまう。
ダブルウィッシュボーン式サスペンションのメリット


「競技用車両やスポーツカーの足廻りならダブルウィッシュボーン!」と言われるほど機能性が高いダブルウィッシュボーン式サスペンションですが、やはりメリットがたくさん!
この項目では、ダブルウィッシュボーンのメリットについてお話しました。
セッティングの幅が広い!
ダブルウィッシュボーン式サスペンションのメリットの一つに、サスペンションのセッティングの幅が広いことが挙げられる。
上記の事から、愛車の足回りのセッティングを自分の好みに調整することが可能なのである。
スポーツ走行重視の一環でコーナリング特性を極めたいだけでなく、通勤快速仕様で乗り心地の良さを追求することも可能なので、とても扱いやすいと言えるだろう。
乗り心地の向上
ダブルウィッシュボーン式サスペンションの一番の利点と言えば、乗り心地の良さが挙げられる。
僕の今の愛車は、30プリウス(3代目プリウス)であるが、30プリウス(3代目プリウス)のリヤサスペンションは「トーションビーム式」である。それが、50プリウス(4代目プリウス)や60プリウス(5代目プリウス)はダブルウィッシュボーン式を採用した。
これによって、乗り心地が大きく向上した。試乗を含めどのプリウスも乗っている僕が感じる違いは、やはりトーションビーム式とダブルウィッシュボーン式の乗り心地の歴然たる違いだ。
先述したEF3シビックのクイックなハンドリング以外にも、あのホイールベースの長い30プリウス(3代目プリウス)や、50プリウス(4代目プリウス)、60プリウス(5代目プリウス)が本当に良く曲がるのに加えて、段差を踏んでも跳ねないリヤサスは感動ものであった。悪路での衝撃をきっちりと吸収してくれるから乗っていて楽なのだ。
サスペンションがダブルウィッシュボーン式に変わっただけで、これほど乗り心地が変わるのかと驚いたぐらいである。
プリウスのように駆動用ハイブリッドバッテリーを載せないといけない車は、乗り心地よりも車内やラゲッジルームのスペース重視であった。30プリウス(3代目プリウス)はそのせいで長いホイールベースにもかかわらずトーションビームが採用されていた。
でも、50プリウス(4代目プリウス)からダブルウィッシュボーン式が採用されたのは、ユーザーの意見などからメーカーが乗り心地を重視したためだと思われる。あの長いホイールベースでトーションビーム式は無理があったのだろう。
車のサスペンションは、左右のサスペンションをトーションバーで繋がれたトーションビーム式なのか、左右のサスペンションがそれぞれ独立懸架されたダブルウィッシュボーンでは、乗り心地は天と地ほどの違いがあるのは事実だ。
そう言えば、上記の画像の30ソアラもかつての僕の愛車だった。この車両も四輪ダブルウィッシュボーンを採用している。車高をベタベタに下げたシャコタン(当時はローダウンとは呼ばずシャコタンと呼んでいた)であったにもかかわらず乗り心地は悪くなかった記憶がある。
安定性と操縦性の向上
独立懸架式の一種であるダブルウィッシュボーン式サスペンションは、乗っていてとても安定している。
カーブに差し掛かった際の左右のロールがあまりなく、車が大きく傾くことが少ないのが特徴だろうか。また、独立懸架式のメリットである片方の車輪が段差を踏んでも、もう片方にその衝撃が伝わることはない。また、悪路や雨天でハンドルを取られることが少なくとてもドライブしやすいのである。
これがリジットアクスル式やトーションビーム式だとこうはいかない。僕の30プリウス(3代目プリウス)は、雨天でリヤタイヤの片方が段差を踏むと前輪のトラクションが掛からなくなりオレンジランプが点灯するのだ。
違う種類のサスペンションの車と乗り比べることで、ダブルウィッシュボーン式の優れたところがリアルに体感できる。ダブルウィッシュボーン採用の車だけを乗っても、具体的な違いは分かりにくいだろう。
マルチリンク式との比較
マルチリンク式サスペンションは、ダブルウィッシュボーン式の進化形だと言われている。
ダブルウィッシュボーン式が上下の2本のアーム(アッパーアームとロワアーム)であるのに対して、複数本のアームを持つのがマルチリンク式だ。マルチリンク式は、ダブルウィッシュボーンが広いスペースを要するのに対し、それを解消して、さらに細かなセッティングをすることが可能だ。
また、マルチリンクは、その構造からロードノイズの振動遮断に優れている。防振構造をしたサブフレームを介して車体へとマウントされることが多いせいだろう。
ただ、進化形と言われるマルチリンク式も、ダブルウィッシュボーンの剛性には敵わない。だから静粛性を求める一般車両よりも頑丈さを求められる競技用車両に採用されることが多いのかもしれない。
マルチリンク式が乗り心地重視なのに対し、ダブルウィッシュボーン式はハンドリングと剛性重視と言えるだろう。
ダブルウィッシュボーン式サスペンションのデメリット


もはや、メリットしか無いのでは?と感じるダブルウィッシュボーンですが、やはりデメリットもあります。
この項目では、ダブルウィッシュボーンのデメリットについてお話しました。
複雑な構造とコスト
構造的に優れたダブルウィッシュボーン式サスペンションにもデメリットはある。とにかく金がかかるのだ。
ダブルウィッシュボーンは、その必要パーツの多さや構造の複雑さから整備の手間とコストがかかるのだ。ひたすら速さのみを追求する競技用車両であれば、コストをかけてレースに勝利するというのは当然のことであっても、市販車は同じように考えることはできない。
セッティングの自由度の高さは却って、高コストになってしまうというデメリットとなる。だいぶ以前の話にはなるが、トヨタの初代エスティマのリヤサスペンションはダブルウィッシュボーン式を採用していた。その他にも何かと話題になった車であった。ところが販売で日産に負けたところから、トヨタは外観を重要視した車を作るようになり、ダブルウィッシュボーン式だったリヤサスはトーションビーム式へとコストダウンを余儀なくされた。
僕は、このようなトヨタの方策に賛成することはできないが、車を販売する側からすれば、仕方がなかったのかもしれない。
取り付けスペースの制約とバネ下重量が重くなる!
ダブルウィッシュボーン式サスペンションは、部品点数の多さから広い取り付けスペースを要することで、荷室や室内が狭くなることだ。国産や輸入車を問わず、サイズの小さいコンパクトカーにダブルウィッシュボーン式サスペンションの採用が少ないのは、そのせいかもしれない。駆動用バッテリーを要するハイブリッドカーも同様である。
また、部品点数が多くなることで、重量が重くなる。車の構造上、「バネ下重量」が重くなるのだ。ダブルウィッシュボーン式サスペンションの採用が多い競技用車両やスポーツカーは、バネ下重量が重くなるのを軽減するために、重量の軽い鍛造ホイールやマグネシウムホイールを採用せざるを得なくなる。
まとめ

今回のお話は、大まかに言って、
●実はこんなに凄い!ダブルウィッシュボーンの特徴
●ダブルウィッシュボーン式サスペンションのメリット
●ダブルウィッシュボーン式サスペンションのデメリット
でしたね。
構造上優れているとされるダブルウィッシュボーン式サスペンションも、デメリットはあります。でも、そんなデメリットを感じさせないぐらいの良さがダブルウィッシュボーン式サスペンションにはあると僕は強く思っています。
毎日乗る車だからこそ快適でありたい!サスペンションの良し悪しはドライバーにとってとても重要な要素だと思うのです。僕の30プリウス(3代目プリウス)もダブルウィッシュボーンであれば良いのにと思うぐらい、ダブルウィッシュボーン式サスペンションは優れています。















-300x200.jpg)
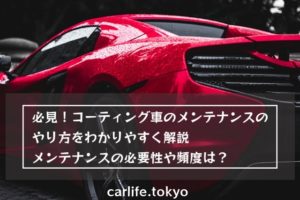




いままで、いろんな車に乗り継いできたり、試乗してきましたが、今更ながら「ダブルウィッシュボーン式サスペンション」のメカニズムの凄さを感じています。このサスペンションはとても良いです!
今回は、ダブルウィッシュボーン式サスペンションの特徴や構造、メリット・デメリットについてお話しました。